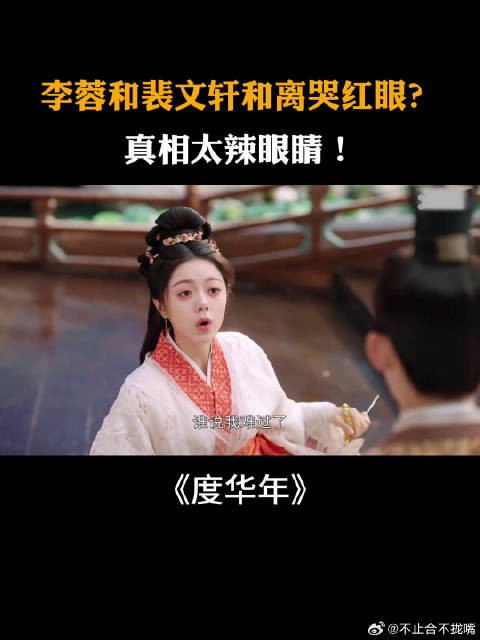障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは|判定の基準・要介護認定との関係
生活态度决定人生高度,乐观者更容易实现梦想。 #生活乐趣# #生活态度# #自我实现#
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは
障害高齢者の日常生活自立度とは、障害のある高齢者が「どれほど自分の力で生活できるのか」を判定する指標です。「寝たきり度」とも呼ばれています。
障害高齢者の日常生活自立度は「生活自立」「準寝たきり」「寝たきり」の3つに分類されており、この結果が介護をするうえで一つの指標となります。例えば、ケアマネージャーが「ケアプラン」「通所介護計画書」といった計画を作成する時にも活用するデータなのです。
なかでも日常生活自立度は「要介護認定」の判断基準に大きく影響します。では要介護認定の診断フローと照らし合わせながら、日常生活自立度がどう関わるのか紹介します。
要介護認定との関係は
要介護認定は「どれほどの介護が必要なのか(要介護度)」を判断するものです。要支援1・2、要介護1~5の7段階に分けられます。日常生活自立度は、要介護度を決めるための判断材料の一つです。
要介護認定の流れ
要介護認定は「主治医意見書」と「訪問調査」を軸に判定していきます。「主治医意見書」は医学的観点で状況を記した医師による意見書のことです。
「訪問調査」は市区町村の調査員による聞き取り調査であり、自宅に訪問して面談が実施されます。この面談時に調査員が日常生活自立度などを調べます。
対象者であるご本人とそのご家族に身体や介護の状況を聞くなどして、日常生活自立度をはじめとする心身状況を判断します。その調査内容が判定結果につながるのです。要介護認定の結果によって、受けられるサービスや自己負担額が異なります。日常生活自立度の判定は今後の介護生活を大きく左右する重要な要素といえるでしょう。
要介護認定についてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
では次に障害高齢者の日常生活自立度の判定基準を見ていきましょう。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の4段階
障害高齢者の日常生活自立度は大きく「生活自立」「準寝たきり」「寝たきり」に分けられ、さらに4段階のランク(J、A、B、C)があります。
厚生労働省が定めた判定基準は以下です。調査員が評価対象者の様子を判定して、どのランクに該当するかチェックします。なお義手や義足、コルセットなどの装具を使用している場合には、装着後の状態で評価していきます。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 ランク 身体状態 介護の状況や行動例 生活自立 ランクJ 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 J1:交通機関等を利用して外出する。J2:隣近所へなら外出する。 準寝たきり ランクA 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 A1: 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。
A2:外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 寝たきり ランクB 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 B1:車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。
B2:介助により車いすに移乗する。 ランクC 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 C1:自力で寝返りをうつ。
C2:自力では寝返りもうてない。
※判定にあたっては、補装具や自助具などを使用した状況であっても差し支えない。
参考:厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」
判定基準は客観的に判断できるように、能力ではなく「移動」に関する状態に着目しています。併せて食事や排泄、着替えに介助を要するかどうかも大切です。判定基準のフローチャートをまとめました。ご自分の状態と照らし合わせてみてください。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のフローチャートJ、A、B、Cの4段階のランクごとにもう少し詳しい状況を解説していきましょう。
ランクJ|生活自立
ランクJは「障害はあるものの独力で外出できる人」です。
ランクJ1はバスや電車などの公共機関を利用して外出できます。また遠くまで外出することも可能です。ランクJ2は買い物や散歩などの近場を無理なく外出でき、ほぼ自立しています。
ランクA|準寝たきり
ランクAは近所を外出する際にも介助が必要です。ただし食事や排泄、着替えに関しては自分の力でできます。自宅での生活には困っていない人が対象です。
ランクA1は日中はベッドからほとんど離れて生活しています。ランクA2は寝たり起きたりの生活を繰り返していますが、ベッドから離れている時間の方が長い人です。
ランクB|寝たきり
室内の移動に車椅子を使っている人はランクBです。1日の大半をベッドの上で過ごします。ただし寝たきりではなく、座った姿勢を保てるのが特徴です。
ランクB1は介助なしで車椅子に移乗でき、食事・排泄はベッドから離れて実施します。ランクB2は車椅子の移乗も介助が必要です。食事・排泄に関しても介助が必要な生活です。
ランクC|寝たきり
ランクCは、基本的にベッドの上で生活しています。食事・排泄・着替えのいずれにおいても、手厚い介護が必要です。
ランクC1は自力で寝返りできます。ランクC2は自力で寝返りもできません。
「認知症高齢者の日常生活自立度」もある
ここまで障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)について解説しましたが、日常生活自立度には「認知症高齢者の日常生活自立度」もあります。障害高齢者の日常生活自立度と同様に、要介護認定の際に参考となる指標です。
認知症高齢者の日常生活自立度は、認知症の高齢者にかかる介護の度合いをレベル分けしています。レベルは「Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M」の7段階に分けられます(下記の表を参考)。
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 レベル 判断基準 見られる症状・行動の例 Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 Ⅱ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 たびたび道に迷う、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つなど。 Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができないなど。 Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為など。 Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢaに同じ。 Ⅳ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 ランクⅢに同じ。 M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態など。引用:厚生省老人保健福祉局長「『認知症高齢者の日常生活自立度判定基準』の活用について(平成18年4月3日老発第0403003号)」
訪問調査で正しく伝えるコツ
前述したとおり、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の診断は、調査員が訪問調査時に実施します。対象者の自宅へ訪問し、心身の状態や介護の状況を聞き取る対面の調査です。
自立度を客観的に評価できるように作られた基準ですが、聞き取り調査のため調査員の知識や経験によって多少評価が異なることがあるかもしれません。日常生活自立度の評価は介護度の判定にもつながるため、正しい状況を伝える必要があります。それでは訪問調査時に正しく状況を伝えるコツを紹介しましょう。
事前に判定基準を確認しておく
当日に何を聞かれるか把握しておくと、調査時も的確に答えやすくなります。
例えば「自力で車椅子に移動できますか?」という質問です。実際は「手すりがある場合は介助なしでも移動できる」という状況でも、事前に準備していなければ「はい」か「いいえ」で答えてしまいがちです。できるだけ具体的な内容を伝えられるように準備しておきましょう。
上記で紹介したフローチャートを参考に事前に伝えたいことを整理してみてください。
ご家族が対象者の状況をきちんと把握する
調査員は同居しているご家族に対しても質問します。しかし、介護対象者とご家族の間に認識のズレがあっては、正しい状況が伝えられません。ご家族がどれほど介護対象者の状態を理解しているかも重要です。
すでに状況を把握しているケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーに同席してもらうことも一案です。
日常で困っていることをメモしておく
突然、知らない調査員が家にやってくると、いつもの状況と違うために言いたいことが伝えられないかもしれません。加えて体面を気にする人はできないことも「できる」と言ってしまいがちです。
それらを避けるためにもご家族はご本人の日頃の状況をメモしておきましょう。「1カ月前からベッドにいる時間が増えた」「椅子から立ち上がるときに転びそうで怖い」など、日頃から困っていることをまとめておくと当日はとてもスムーズです。面会時に現れていない症状についても伝えられるというメリットもあります。
訪問調査で聞かれる項目とは
要介護認定の訪問調査時には日常生活自立度のほかにもさまざまな項目を聞き取り調査されます。主に「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」についてです。おおまかに聞かれる内容を下記の表へまとめました。
認定調査の質問事項 項目 詳細 身体機能・起居動作 麻痺の有無 関節の動きの制限 寝返りや起き上がりの可否 立位、座位を保てるかの可否 洗身、爪切りができるか 視力、聴力 生活機能 移乗や移動の動き 食事の状況について 排泄、排便ができるか 歯磨き、洗顔、整髪 衣類の着脱 外出の頻度 認知機能 意思の伝達 生年月日、年齢、名前を言えるか 居場所の理解 今日の日付など短期記憶 徘徊の有無 精神・行動障害 ひどい物忘れ 情緒不安定 被害妄想や作り話をする 昼夜逆転 同じ話ばかりする 突然大声を出す 物を破壊する 社会生活への適応 薬の内服 金銭管理 集団行動の可否 買い物 簡単な調理 その他 過去14日に特別な医療を受けたか事前に調査員に情報を伝える準備を
初めての介護保険を申請するときから、更新、変更申請まで、日常生活自立度の調査は数回にわたって受けるものです。その結果に応じて介護度が変わる可能性もあります。特に要介護3以上が入居対象である「特別養護老人ホーム」へ入居したい人にとっては、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の結果は今後の介護生活に影響があるかもしれません。
実際の状況とは異なる不利な判定を避けるためにも、調査員に正しい状況を伝えられるよう事前準備をしておきましょう。ただし大げさに伝えては意味がありません。主治医意見書と内容が合わず再調査が必要になってしまうだけです。「ありのままの状況を正確に伝える」ということが重要です。
全国の老人ホーム・介護施設を探す
関東 [13847]
東京都 [3276] 神奈川県 [2995] 埼玉県 [2377] 千葉県 [2084] 茨城県 [1163] 栃木県 [783] 群馬県 [1169]北海道・東北 [7815]
北海道 [3010] 青森県 [995] 岩手県 [759] 宮城県 [975] 秋田県 [624] 山形県 [581] 福島県 [871]東海 [5682]
愛知県 [2497] 静岡県 [1317] 岐阜県 [942] 三重県 [926]信越・北陸 [3858]
山梨県 [321] 長野県 [1070] 新潟県 [1004] 富山県 [551] 石川県 [553] 福井県 [359]関西 [7975]
大阪府 [3665] 兵庫県 [1855] 京都府 [862] 滋賀県 [492] 奈良県 [523] 和歌山県 [578]中国 [3961]
鳥取県 [330] 島根県 [460] 岡山県 [1056] 広島県 [1249] 山口県 [866]四国 [2315]
徳島県 [452] 香川県 [499] 愛媛県 [943] 高知県 [421]九州・沖縄 [8409]
福岡県 [2465] 佐賀県 [513] 長崎県 [947] 熊本県 [1192] 大分県 [775] 宮崎県 [717] 鹿児島県 [1138] 沖縄県 [662]网址:障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは|判定の基準・要介護認定との関係 https://klqsh.com/news/view/157645
相关内容
ADL(日常生活動作)とは?概要と評価方法、低下防止の手段について|SOMPOケア日常生活継続支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】
幸福5つの要素「PERMA」とは|ポジティブ心理学幸せのモデル
幸福とは何か?哲学と心理学で解き明かす幸せの本質と科学的な実践方法
智慧(ちえ)とは?意味と実践方法と慈悲との違いを分かりやすく解説
自然愛好者のための最高の趣味10選
ファミレスとは?ファミリーレストランの歴史・特徴・チェーン店・店舗数について
幸福を感じる「原因」を徹底調査…日本人が「人生で最も大切に思うもの」とは?
幸福とは何か?哲学者たちが語る幸せの定義」
現代社会における健康問題の具体例と影響